◎ 原則課税と簡易課税 どちらを選ぶ?
原則課税 と 簡易課税 どちらが有利? その注意点は?
人毎 ・ 法人毎の <売上高> で、それが届出等にも影響します
| 簡 易 課 税 | 原 則 課 税 | |
|---|---|---|
| ど ち ら が 得 | 試算してみないとわからない | |
| 届 出 | ◆ 今期から (不) 適用したい場合 前期末までに届出が必要 | 届出不要 |
| 継 続 適 用 | 選択すると、2年間は継続適用 (※) | - |
| 計 算 ・ 注 意 点 | ◎ 課税売上高に関し、相殺があった 場合に注意 2年後の期は適用できない | ◎ 仕入税額控除は請求書等がない と認められない <例> 給料、保険料、租税公課等 給与になるのかの判定に注意 |
日の属する課税期間の初日以後でなければ、取り止めの届出書
を提出できません (消法 37条③)
| 簡易課税選択届出書 | → | (1) | 基準期間における課税売上高が、5000万円を 超えると出せない |
|---|---|---|---|
| (2) | 翌々期から適用すると提出しても、翌課税期間 から適用となります |
ずっと残ったまま → 注意が必要です!! (消法37②) (消基通13-1-3)
| どういう場合 | → | 届 出 書 | 提出 期限 等 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 簡易課税の選択を止めるとき | → | 『選択不適用届出書』 を提出 | ⇒ | |
| (2) | 事業を廃止したとき | → | 『事業廃止届出書』 を提出 | (注) | |
| (3) | 法人成りし、個人事業を廃止したとき | → | 『事業廃止届出書』 を提出 | ||
すべて取り止めたものと取り扱われます (<例> 簡易課税の選択の届出等)

消費税の原則課税と簡易課税の選択。 どちらが有利か? 今一度試算してみましょう。
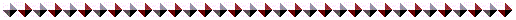
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/